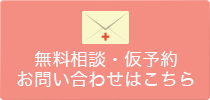骨を吸収しにくい構造 プラットフォーム・スイッチング
インプラントと一概にいっても、現在世界中では100種類以上も作られています。
日本製のものもいくつか作られており、歯科医は患者様の状況や費用などに合わせて選んでいます。
加藤歯科医院でもEBiインプラント、ITI、マイティスをメインに使用しています。その中で今後のインプラント治療の主流となりえるインプラントシステムがプラットホーム・スイッチングです。
プラットフォーム・スイッチングとは
インプラントは、大きく分けて 3つの構造(パーツ)からできています。

- フィクスチャー (インプラント本体・人工歯根)
- アバットメント(土台)
- 上部構造(被せ物、補綴物)

手術の際、インプラントは必ずどこかの部分で歯槽骨の中から歯ぐきの粘膜部分を貫通しなくてはなりません。実はここがインプラントの弱点部分です。この貫通部分に細菌が繁殖しやすく、炎症すると骨を吸収してしまうのです。
骨の吸収はおおよそ数年で約1~2ミリと極わずかと感じるかもしれませんが、たとえばインプラント体は全体で10ミリ程度ですので、きちんと埋まっていたとしても2ミリも骨に吸収されてしまうと残りは8ミリになり、耐久性は損なわれ、骨吸収が起こることで歯ぐきの退縮も起こり、アバットメントがむき出しになり審美性でも問題が生じてしまいます。
これを防ぐために一つの考え方として、この歯肉の貫通部分をなるべく小さくしようといった考え方が出てきました。乱暴な説明ですが、インプラントとアバットメントの接合部分に「くびれ」を作ったのです。それがプラットフォーム・スイッチングです。
プラットフォーム・スイッチングでは、接合部が内側に設定されるため、インプラントと骨との接合部が粘膜で覆われ、結果、歯肉の厚みが増えることになります。
歯肉の厚みが増えると血流量も増え、細菌に対する粘膜の抵抗力も増える。これで、骨の吸収を防ぎ、歯肉の退縮も防ぎ、審美的にも機能的にもインプラントが長持ちすることにもなります。

虫歯にならないインプラントではありますが、きちんとケアをしていないと「インプラント周囲炎」と呼ばれるいわゆるインプラントの歯周病となる可能性もあります。細菌への抵抗力も増すことによって、インプラント周囲炎へのリスクが減るということです。
プラットフォーム・スイッチングにはインプラント手術を受ける患者様にとってさまざまなメリットがあります。今後も加藤歯科医院ではより長くインプラントを使っていただくための治療として利用していきたいと思います。